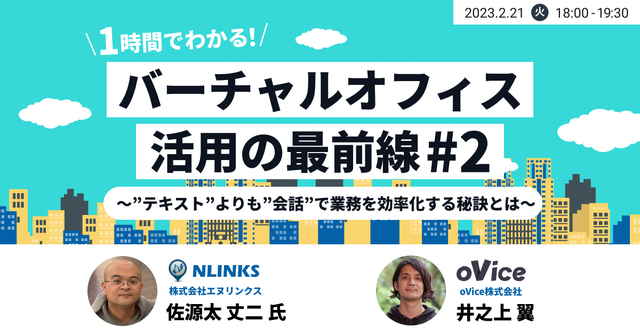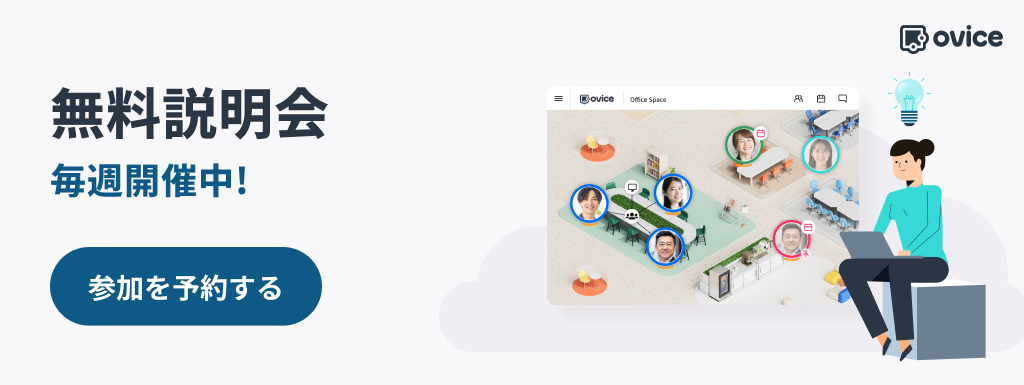化石型の古い経営者にとっては頭の痛い時代だろう。
「働き方改革」「ワーク・ライフ・バランス」などという言葉が登場したかと思えば、新型コロナウイルス感染症対策のため導入せざるをえなかった「テレワーク」「リモートワーク」が半ば強制的に現実のものとなり、その収束とともに「ハイブリッドワーク」や「ワークライフチョイス」など実に様々な働き方が定着、さらには「どの働き方を選択するのか」と「フレキシブルワーク」の実践が求められる時代がやって来た。
ただし今後、「フレキシブルワーク」は多くの経営者にとって真摯に向き合わなければならないテーマだろう。
目次
「フレキシブルワーク」ありとあらゆるワーキングスタイルの可能性
そもそも「フレキシブルワーク」とは、どう定義されるのか。
それは「働き方改革」のゴールともされるべきワーキングスタイルとして良いだろう。昭和の時代まで「働き方」とは、定められた就業時間に物理的に出社し、残業を命じられ、退社するという固定された場所、時間に限定された労働だった。せいぜい営業などの外勤とされるメンバーが直行、直帰などを許される程度で、会社に姿を見せないのは「働いていない」と同義だった。
しかし、インターネットに代表されるテレコミュニケーションの発達により、必ずしも出社によらないワーキングスタイルが誕生、働く場所・時間を柔軟に選択可能な時代へと移行したのは、ご存知の通り。今では海外出張先からでさえ、ほぼ通常通り業務遂行が可能だ。海外からFAXで原稿を送信し、国際電話で業務をこなしていたら、ホテルの電話代が10万円を超えていた…というのは完全な昔話である。
しかも、そのワーキングスタイルはもはや「出社 or 在宅」などの二者択一の勤務形態ではない。かねてより導入されていたパートタイム制やフレックスタイム制も含め、契約社員、派遣社員、フリーランス、業務委託、さらに副業にジョブシェアの導入まで、正社員とは異なるありとあらゆるワーキングスタイルの確立が「フレキシブルワーク」となる。
また、正社員も含めリモートワークによって可能となったサテライトオフィスの活用、ワーケーションなど、実に柔軟な働き方ももちろん含まれる。
関連記事
サテライトオフィスとは?メリット・デメリットと導入時のポイントを紹介
ワーケーションとは?メリットや導入手順、企業の先進事例を解説!
フレキシブルワークは、社員のワーク・ライフ・バランスの好転を促し、その勤労意欲・幸福感の向上へとつながる。こうした社員生活の柔軟性確保により、一方では企業の生産性・収益性の向上へと寄与する。さらに、常に不足しがちな労働力を様々な形態により補い、企業価値を高める制度として機能する。裏を返せばフレキシブルワークへの理解を示さない企業は、少なくとも先進国において、労働力の確保に後れを取り、今後は衰退の一途を辿る可能性が高まると考えても良さそうだ。
フレキシブルな働き方の歴史
ひょっとすると、まだフレキシブルワークという言葉そのものに馴染みがない日本人も少なくないかもしれない。しかし、ヨーロッパでは1993年にはEU(欧州連合)において、旧労働法の見直しが進み、イギリスではEU労働時間指令(Working Time Directive)に基づき1998年に労働時間規則(Working Time Regulations)を導入、週の労働時間は48時間と限定された。
オランダでも「柔軟性と保障法」が1999年に議会を通過。「フレキシブルワーク」という概念も早くから芽生え、2000年以降は度々法改正を実施、その実効性は加速度的に増して行った。
こうした制度の導入はもちろん他ヨーロッパ各国でも進み、スウェーデンでは2013年の時点で企業の8割がフレックスタイム制を導入。デンマークでは現在、97%が同制度を導入済とされる。
フランスではそもそも個人による多重労働契約は合法で自由。2000年代には「個人が複数の雇用者のもとで就労する」法整備も進められ、副業、マルチ・ジョブは極めて一般的だという。
<参照>リクルートワークス研究所|Works Report 2018
フレキシブルワークを妨げた、日本の封建的主従関係
欧米では20年以上前にはじまったフレキシブルワークだが、日本で「働き方改革関連法案」が可決、公布されたのは2018年。欧米にちょうど20年後れを取っており、ワーキングスタイルの膠着は日本経済の「失われた30年」を生み出すひとつの要因だったと考えられる。
では、なぜ日本ではフレキシブルワークという概念の芽生えがなかったのか。
ひとつは、哲学的に封建制度の主従関係が昭和に至るまで継続された点だろう。もちろん、封建制度はヨーロッパにおいても広く流布、定着していた。しかし産業革命と市民運動の高まりにより17世紀にはそれも終焉を迎える。フランス革命によるアンシャン・レジームの崩壊など、その典型的な例だ。貴族としての身分は残ったものの、「主従関係」という概念は20世紀に至るまでに形骸化していたとして良い。
しかし日本における封建制度は江戸時代まで長らく続き1868年、明治時代の到来を待たねばならなかった。幕末の動乱期を眺めても当時「脱藩」などは裏切り行為の最たるもの、これが人材の流動を抑制していたのは明らかだ。
日本では、ほぼ明治期のスタートとともに産業革命が始まり株式会社が興る。これに伴い哲学的に「藩主=藩士」の封建的な主従制度は、そのまま会社組織における「雇用主=従業員」という図式に置き換わったとみて構わないだろう。
つまり日本では封建制が終焉を迎えたにもかかわらず、資本主義の中に封建的主従関係だけは思想として引き継がれてしまった。ゆえに企業への就職は終身雇用を意味し、日本の就職は「就社」と揶揄される所以となった。「脱藩」同様「転職」は会社に対しての裏切り行為とさえ見られた。
転職は「キャリアアップ」それとも「職を転々」?
欧米では転職し「キャリアアップ」と捉えられるものの、日本では「職を転々とする」という言葉の通り、職を変更するのは、悪しき習慣とされているのも無関係ではないだろう。もちろん、主従関係ゆえ会社の命令は絶対に等しい。経営側は「主(あるじ)」、社が決めたフレキシビリティの一切ない就業規則に異を唱えるなど言語道断。天につばする行為だった。
現在も、従業員を自身に「従う者」と考える化石型「昭和のおっさん」経営者も決して少なくない。定年後も雇用延長により「会社にしがみつく」従業員を生み出してしまったのは、主である雇用側の責任でもある。
労働人口激減とゼノフォビア
また、日本におけるもうひとつの要因は潤沢な労働人口だろう。ご存知の通り日本の人口は1億2000万人を超え、これまでは労働人口に事欠かなかった。
先進国G7でこれを超えるのは3億3000万人を抱えるアメリカのみ。日本に次ぐ国はというと、ドイツの8300万人、イギリスの6700万人と労働人口も内需も小さい(2023年国連発表)。よってワーキングスタイルを改善してまで労働人口の確保に走る必要に迫られて来なかった実情があった。
しかし日本は急速な人口減少に超高齢者社会が追い打ちをかけ、労働人口を劇的に失いつつある。内閣府によると2065年の日本の人口は8800万人程度と予見され、労働力激減の近未来が見える。
令和4年版高齢社会白書によると、日本の労働生産人口は2020年時点で7,509万人だったが、2065年には4,529万人までに減少すると予測されている。移民政策に著しく厳しい日本では、外国籍人口の流入による労働人口増加はない。
<参照>内閣府|令和4年版高齢社会白書
ゼノフォビア(Xenophobia)=外国人恐怖症の日本人は、難民さえも収容所に放り込み、隙あらば自国に送り返そうとするほどだ。アメリカ、ドイツ、イギリスなどすでに移民が労働人口を支えている国々と大きな隔たりがある。リシ・スナク英首相はインド系移民二世だが、日本で肌の色が異なる移民二世の首相が誕生するには、あと100年ほどはかかりそうだ。
先んじるは「優良企業」
日本におけるこうした労働人口の変革を考慮すると「優良企業」が、先んじて優秀な人材を獲得、労働力の確保に向かう。
これまでも本稿で示して来た通り、マイクロソフト、NTT、ヤフー、サイバーエージェントなどなどのIT関連企業は軒並み「どこでもワーク」と称するように、ワーク・スタイルを限定しないフレキシブルな働き方を導入済であり、この流れはさらに促進される。企業にとっても社員にとってもメリットが大きいだけに、逆行は想定しにくい。
関連記事:
【NTT担当者に聞く】NTTは日本の働き方の多様性をけん引するのか ハイブリッド・ワーク勤務地は自宅宣言
マイクロソフトは日本における「リモートワーク」のパイオニアだったのか
「出社したくなるオフィス」、サイバーエージェントが具現化した可変性とABW 強制とモウレツは時代遅れ
最近では、実際に出勤が求められる医療・介護などを含む、いわゆる「エッセンシャルワーカー」業界においても、子育て支援の一環などで「午前のみ勤務」や「午後のみ勤務」と正社員でもワークシェアリング制度の導入が進んでいる。この潮流は、これは決して大企業のみならず、個人経営の店舗などにまで及びつつある。
この時代に至っても日本の化石型経営者はいまだフレキシブルワークを不要とみなしているだろう。主従関係が頭にこびりついて離れない「フレキシブルワークなんかで喰っていけるか」と豪語する昭和のおっさんたちは、絶滅のその瞬間がやって来るまで時代の変化に気づかない。そして「その時」がやって来た際、働き方に自由もないそんな企業に残る従業員はいない。
「そして、誰もいなくなった」そんな終焉は目に見えている。封建的主従関係幻想の継承者は、滅び行くのみ……だ。