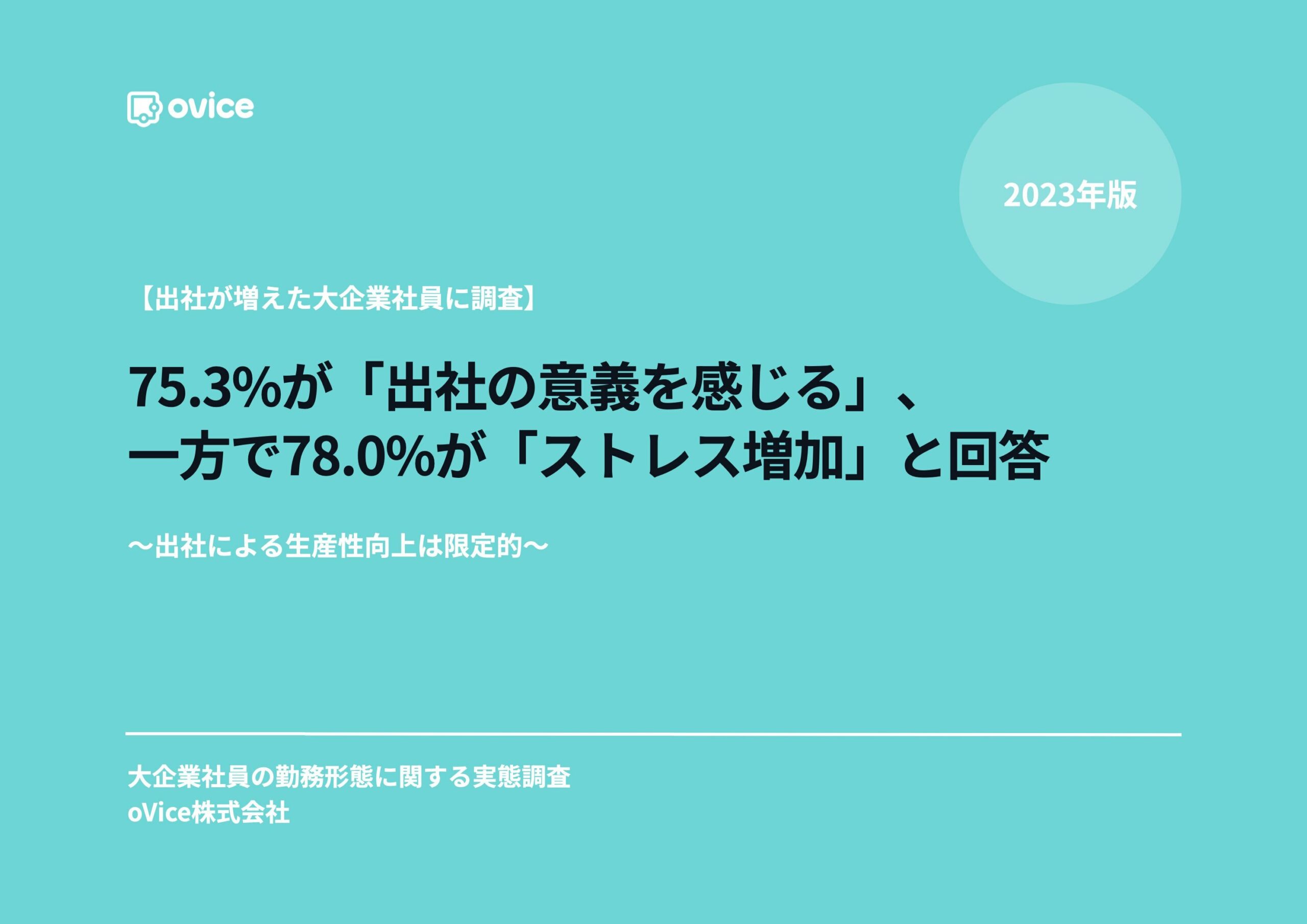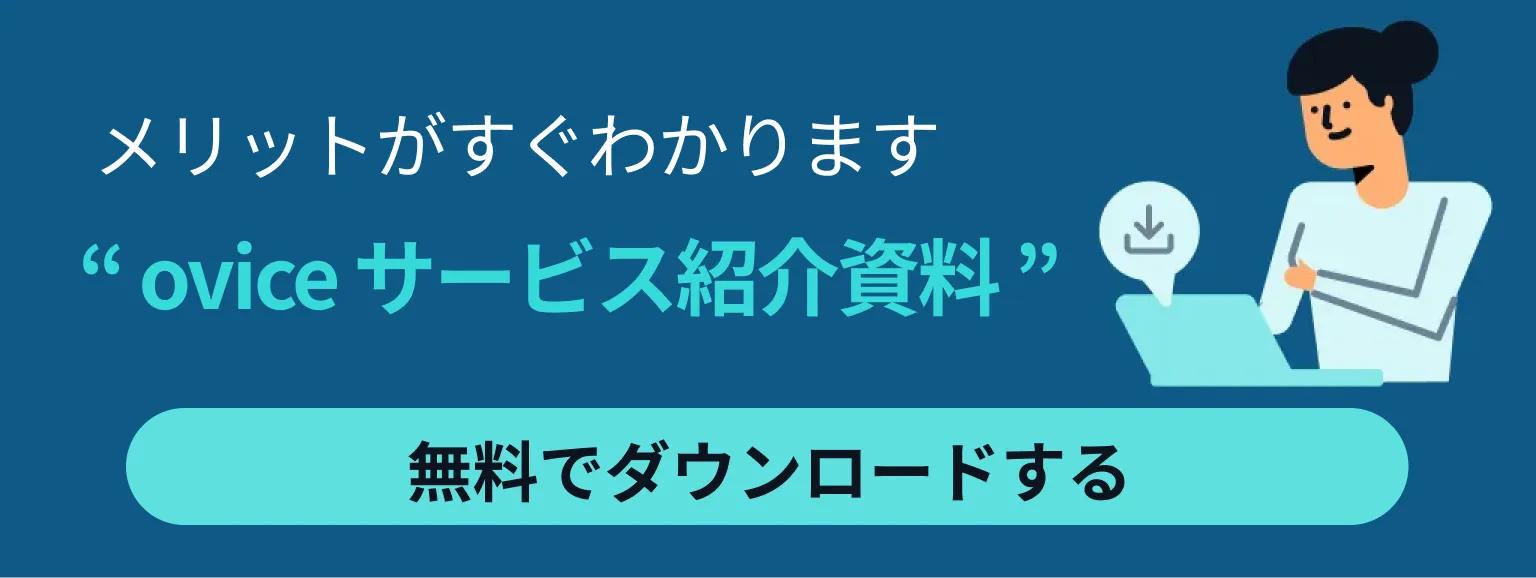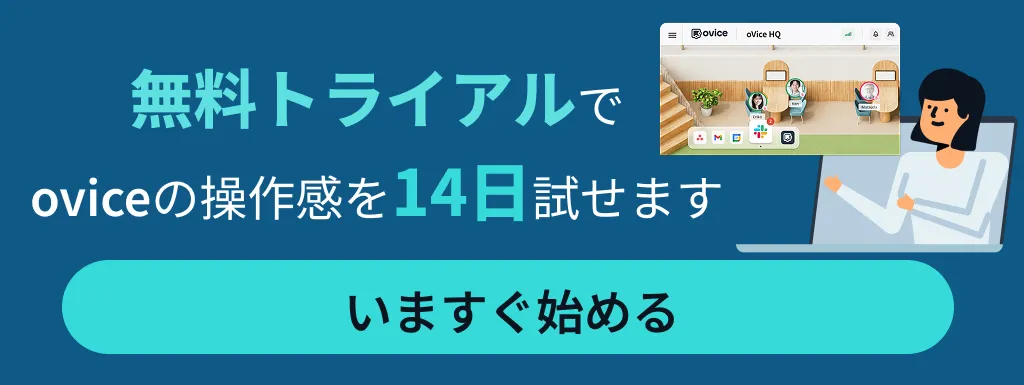昭和の時代、ティーンの味方と言ったらラジオだった。
特に深夜番組。「オールナイトニッポン」という名物番組があり、中島みゆき、ビートたけし、松任谷由実、アルフィーなどなど多士済々がパーソナリティを務め、翌日の学校でもその話題でもちきりとなることもあった。昭和の時代はまだ、はがきを送るというオールドスタイルで、コーナーによっては自身の投稿が読まれるのではないかとどぎまぎしたものだ。
「ものだ」と断定し、過去のように扱おうと考えたところ、現在も星野源などをラインナップ、今も人気を集めていると知る。深夜に音声だけに神経を集中することから、まるでパーソナリティが自分だけに話しかけているのだと錯覚し、それにゆえにラジオは極めてインティメイトなメディアとして歩んで来たと思われる。
知覚依存度の80%以上を占める「視覚」をオフにしてみる
『産業教育機器システム便覧』(日科技連出版社)によると五感による人間の知覚依存度は「味覚1.0%、触覚 1.5%、臭覚 3.5%、聴覚 11.0%、視覚 83.0%」とされ、おおむね人が得る情報の80%は視覚によると言う。
ラジオは、この80%の視覚を活用せず、あえて11%の聴覚に訴えるメディアであり、それがゆえにインティメイトな感情を醸成しやすい傾向にはあるのだろう。昭和の時代には、深夜に長電話するなどの行動もあり、聴覚のみに依存した長電話が「親しい友人」を生むなどという構図も存在した。今の若い世代は、メッセンジャーでのやり取りが大半を占め、音声による通話などもあまり利用しないとのこと。2019年に総務省が発表した「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、10代が利用するコミュニケーション手段のうち71.6%がSNSを使用、IP通話も5.1%、携帯電話による通話も3.1%に過ぎず、固定電話は0%だった。
しかし、聴覚を介した情報収集がまったく葬り去られたかと鑑みると、決してそうではなさそうだ。アプリでラジオ視聴が可能なradikoは800万人以上のユーザーを抱え、その有料版も70万人を数える。Voicyの年間ユニークユーザーも1000万人を超え、招待制のClubhouseなど新しいアプリの登場もあり、聴覚に依存したインティメイトなメディアは粛々と活用され続けると見て取るべきかもしれない。
リモートワークでも、もっと「聴覚」を活用してみては
これを考慮に入れるのであれば昨今はメタバースが世間を賑わせ、視覚に依存したXRがもてはやされる時代となってはいるものの、音声を活用したコミュニケーションも決してないがしろにすることはできない。
リモートワークなどは、聴覚という観点にはもう少々スポットライトを当てるべきではなかろうか。
リモート会議の際、資料などを共有する場合を除けば、むしろ画像をオフにし、音声のみの会話のほうが集中力が保たれるケースもあろう。特に慣れ親しんだメンバーであれば、カメラをオフにし、どんな格好をしているとか、バックグランドを何に設定しているとか、あってもなくてもどうでもよい知覚情報の80%を遮断することで、音声に集中し、むしろ言葉を理解しやすく、要点を得やすいように思われる。私の周りでは、リモートツールをつなぎつつカメラをオフにし、いつでも話しかけられる環境を維持している20代社員も多い。
「Dialog in the Dark」では言語コミュニケーションが活性化
これは私の思い込みではないかと考えもしたが、こんな事例もある。
視覚障害者疑似体験を行う手法として、「Dialog in the Dark(DID=ダイヤログ・イン・ザ・ダーク)」はよく知られるところ。ドイツ人哲学者アンドレアス・ハイネッケによって考案されたとされる。これは視覚障害者を知る上で、可視光線を遮断した空間内で活動するという疑似体験。要は真っ暗闇の中で行動するとは、どういう状況かを味わってもらおうというわけだ。
この体験では視覚が失われることで他の4つの感覚が敏感になることが判明。さらに周囲の人に自身の存在を認識してもらうため、言語によるコミュニケーションが活性化されるという副次効果も認められている。
視覚を遮断されることで、ノンバーバル・コミュニケーションが制限されるため、純粋なバーバル・コミュニケーションが促進される。これはリモートでのコミュニケーションにおいても、音声のみのほうが会話に集中できるという傾向を意味している。
元来、聴覚は脳にダイレクトに作用し、人が死ぬ間際に最後に失う知覚ともされている。
ビフォー・コロナ禍と異なり、リモート飲み会やリモート懇親会ももはや物珍しい時代ではなくなかった。しかし、数人の飲み会ならいざしらず、人数が増えれば増えるほどモニターに表示されても誰が誰だかわらないサイズに。そうとなれば、カメラオフ、音声のみのほうが効率的だ。だが、ビデオ会議ツールで画面オフにすれば、真っ暗な画面やユーザー名が並ぶだけでなんだか味気なかったりさみしさを感じたりするだろう。
例えば、バーチャルオフィスoviceのような、基本カメラオフとしたアバターでの交流がある。聴覚に訴え言語野に響くインパクトを備えるので、会話をメインとしたコミュニケーションにはうってつけなのではないかと考える。大きなヘッドギアを装着し最新のメタバースの世界にはまり込むのも一興であり、近未来に没頭できそうな時代となっているのは確かだ。一方で、聴覚への依存度を高めコミュニケーションの活性化を図るのもひとつの方法論であるという点は、忘れてはならない。

_画像01.jpg)