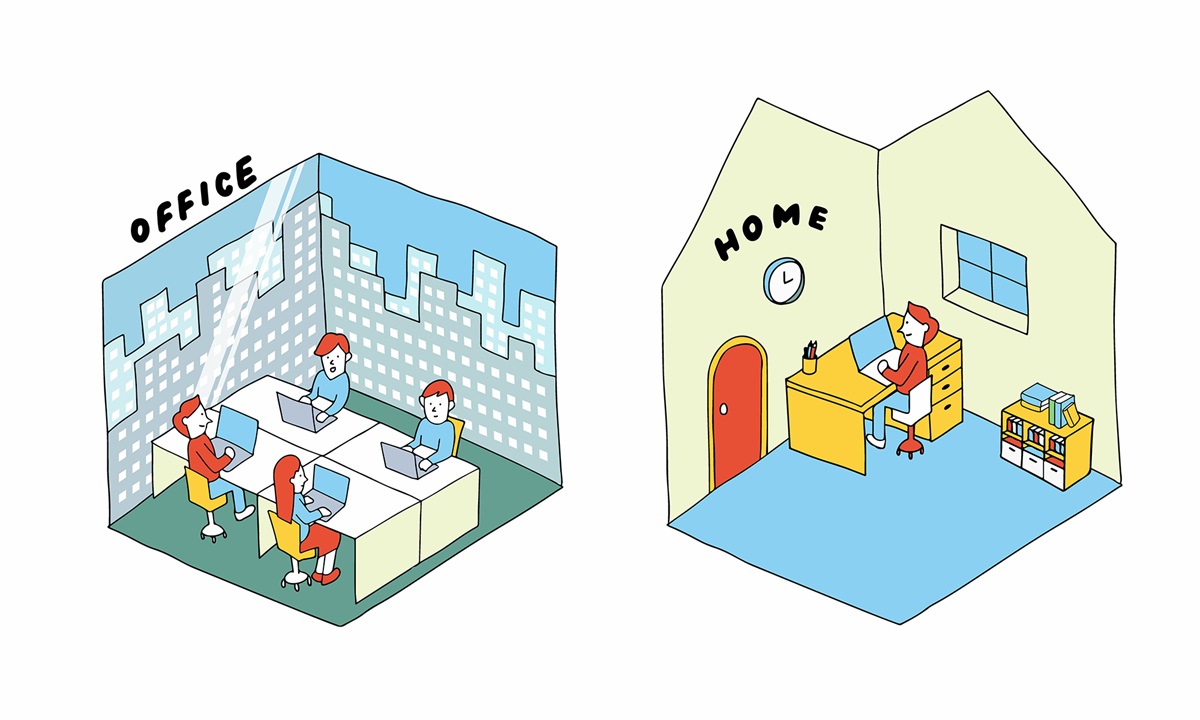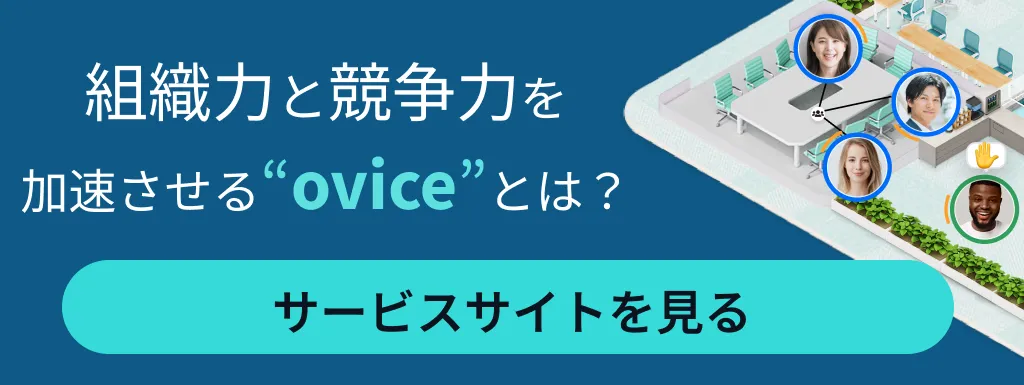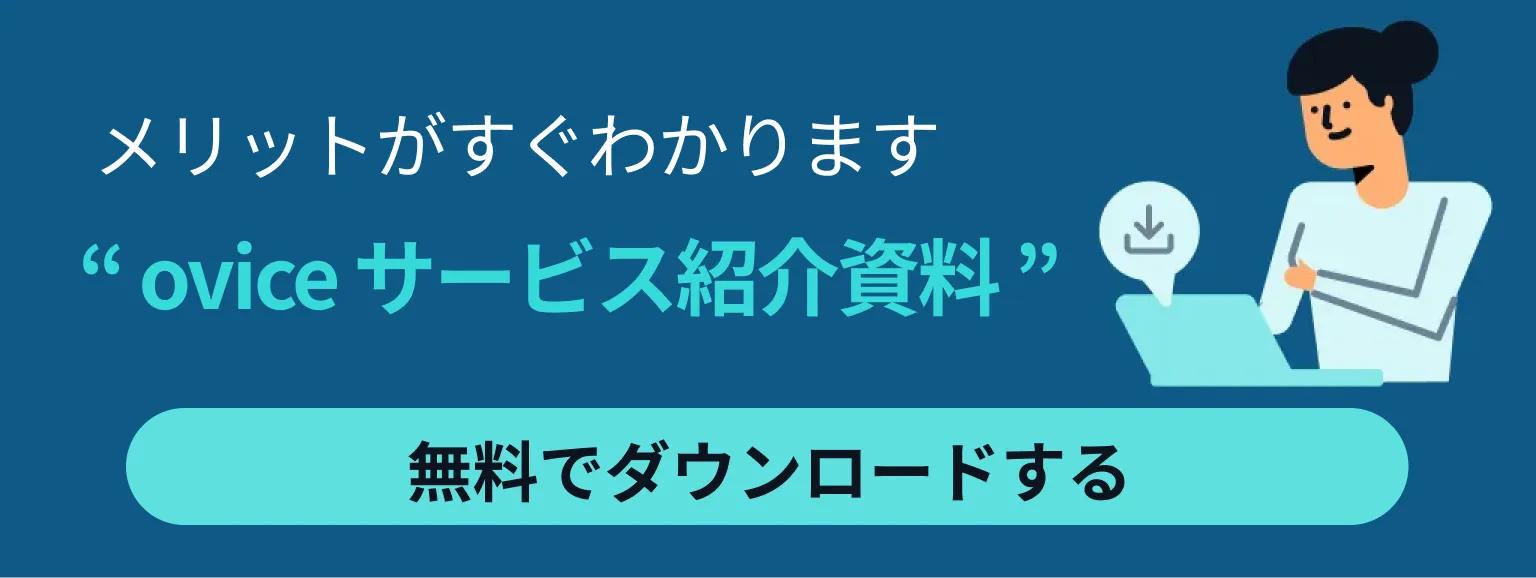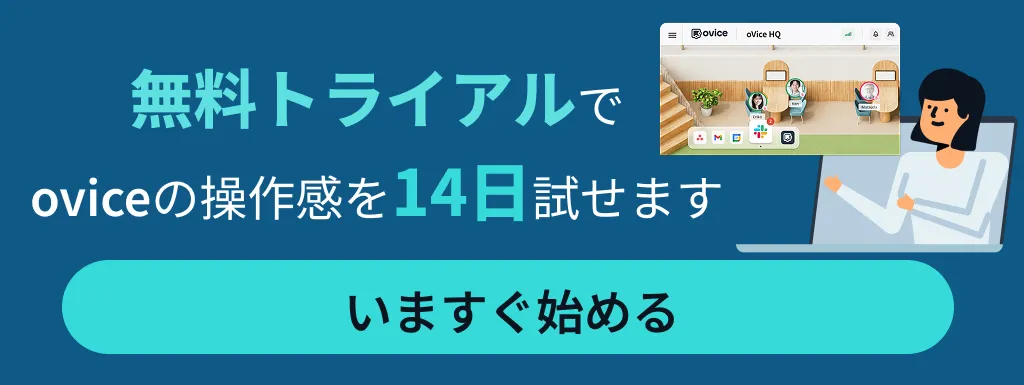新型コロナウイルスが5類感染症に指定された2023年5月以降、多くの企業が物理的なオフィスへの出社回帰を進める様子が見られました。一方、出社回帰したことで課題を感じている企業も少なくありません。この記事では、出社回帰によって直面する8つの課題とその解決策について紹介します。
目次
様々な「出社回帰」の選択肢
オフィスへの出社回帰と一口に言っても、その形は様々です。まずは4つのパターンに分類してみます。
パターン(1) 完全出社型
まず挙げられるのが、全社員のオフィス出社を要求する、完全出社型。コロナ渦以前には多くの企業が取り入れていたため、多くの方が馴染みのある働き方です。
しかし、リモートワークに慣れた方にとっては負担も大きく、パフォーマンスが下がったり離職してしまったりというケースも少なくありません。
パターン(2) ハイブリッドワーク(部門型)
新しい働き方として注目を集めているのが、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークです。出社とリモートワークの組み合わせには様々なパターンがありますが、その一つに部門別での運用があります。
たとえば、「エンジニアなどの職種はリモートワーク」「書類を多く扱う職種は出社」というようなルール設計です。
パターン(3) ハイブリッドワーク(出社日固定型)
ハイブリッドワークのパターンには、出社する日数が決まっているケースもあります。
ある曜日は出社日というように出社する日が決まっているパターンもあれば、週〇日以上と好きな日に出社できるパターンも存在します。
また、部門型と組み合わせた運用もみられます。A部門は週△日出社、B部門は週XX日出社など、部門によって出社日を自由に決められるケースもよく見られます。
パターン(4) ハイブリッドワーク(裁量型、融通型)
従業員の裁量によって、出社かリモートワークかを選択できるワークスタイルです。基本は在宅で仕事をしながらも、必要に応じて出社することで、従業員それぞれの働き方のメリットを享受することができます。あるいは、たとえばアイディアを出し合うブレインストーミング会議など対面で集まった方が効率的な場合は、オフィス出社を選択することができます。
必要なときだけオフィスに出社すればいいので従業員の負担が少ない働き方ですが、コミュニケーションをとりたい相手が出社なのかリモートなのかわからず、「相手をみつけにくい」「(その結果として)コミュニケーションをとるタイミングを逃してしまう」といった事態が起こることもあります。
▼関連記事
オンラインでブレスト活性化!独創的なアイデアを生み出すポイントを解説
リーダー必見!ハイブリッドワークにおける6つの心得
オフィスへの出社回帰で生じる8つの課題
続いて、オフィスへの出社回帰で企業が直面することの多い、8つの課題について紹介します。これらの多くは、特にパターン(4)の場合に注意が必要といえるものですが、パターン(1)、パターン(2)、パターン(3)にも共通してみられる問題もあるので参考にしてみてください。
課題(1) 出社組とリモートワーク組のコミュニケーション
1つ目の課題は、出社組とリモートワーク組のコミュニケーション格差が生まれてしまうことです。
リモートワークの普及に伴い、世の中には様々なコミュニケーションツールが誕生し、日本でも日常的に使われています。しかし、それらの多くは従業員が基本的に在宅勤務をしている前提でした。
出社している人と在宅勤務の人が混在している中では、相互のコミュニケーションがうまくいかなかったり、意思決定が遅れてしまったりするリスクがあります。
課題(2) 従業員のマネジメント
マネージャーからしても、出社組とリモート組が混在することで、マネジメントが難しくなります。出社している部下は上司にも相談しやすいため比較的早くフォローできますが、オンラインでは相談するハードルが少し上がってしまいます。「こんなことで相談していいのかな」と考えているうちに、課題が深刻化することも珍しくはないでしょう。
マネージャーは、リモートワークの部下と出社している部下に対して接し方も変えなければいけません。「この時間はオンラインでもオフラインでも自由に話しかけて良い」といったメッセージと、それを可能にするオンラインツールの導入は一つの解決策となります。
▼関連記事
社内での声かけ・雑談がチームにもたらす3つのメリット
課題(3) 従業員のワークライフバランスの確保
リモートワークのメリットの一つが、ワークライフバランスを確保しやすいことです。特に子育て世帯などは、リモートワークで助かった方も多いでしょう。そのような方は、出社を要請された場合に、プライベートをこれまで通り保つために大きな負担が生じると感じるかもしれません。
仕事とプライベートのバランスがとれないことは心労につながり、仕事にも大きな影響を与えてしまいます。全員が出社する必要があるのかを再確認してルールを設計しなおしたり、家庭の事情で在宅勤務を希望できる制度を制定したりすることによって、こうした課題が解決することもあります。
課題(4) 人材確保
オフィスへの出社回帰を実施した会社の中には、従業員が立て続けに離職してしまうケースもあります。リモートワークのよさを感じた人の中には、出社に戻りたくないという方も多く、リモートワークができる企業に転職してしまうこともあるようです。出社回帰のパターン(1)を実施する場合には、インセンティブをしっかり用意する必要があるでしょう。
▼関連記事
人手不足を解消するには?採用・育成・業務効率化の3つの視点
課題(5) 会議室・席の不足
企業の中には、コロナ禍の間にオフィスを縮小したり、解約した企業も少なくありません。そのような企業がオフィスへの出社回帰を実施すると、席や会議室が不足してしまう事態に陥ります。特にオンライン会議が増えた現在は、周囲への声の干渉を気にせずに話せるスペースの必要性を感じることも多いはずです。
オンライン会議のスペースが足りず、場所を求めさまよう様子は一時「Zoom難民」などと表現されたこともありました。会議室がとれない場合には、場所を移したりリスケしたりという解決策を取るとの調査結果もあります。
<参照>
PressWalker | 【調査レポート】オフィス回帰で新たな課題、「会議室足りない」が5割
適切な環境でなければ会議に集中できなくなってしまうことも考えられますし、リスケにいたってはタスク処理の進行を止めてしまうことを意味しています。オフィスへの出社回帰で再びこのような状況が増えてしまうと、生産性を大きく下げてしまうといえるでしょう。
課題(6) 出社頻度の格差・不満が生まれる
ハイブリッドワークを採用する場合に、部署やチームによって出社頻度を決めるケースも少なくありません。
週4日出社が必要なチームと週1度の出社でいいチームがいれば、出社が多いメンバーは不満を感じるかもしれません。職場の清掃を社内で担当制としている場合なども配慮が必要です。
社内で極端な格差が生まれていないかを確認し、しがらみが生まれないような調整を行うとよいでしょう。
課題(7) 従業員のモチベーションが低下
オフィスへの出社回帰で、離職するほどではないにしろ、仕事へのモチベーションが下がることは大いに考えられます。
たとえオフィスでの時間が充実したものであっても、満員電車に乗って通勤するだけで気力も体力も削がれるものです。家でもできる仕事をわざわざオフィスでやるための出社なのであれば、余計にストレスがたまることも想像に難くありません。
「なぜ出社する必要があるのか」を明示することは、こうした心理を防ぐことにもなるでしょう。
▼関連記事
心理的安全性とは?組織のパフォーマンスを高める具体的アプローチ
課題(8) 賃料の負担
オフィスへの出社回帰によって社員を物理的なオフィスに呼び戻すとなると、当然そのための場所を維持するランニングコストがかかります。
メンバーの出社を前提に考えればロケーションも重要ですし、そのようなエリアは必然的に賃料も高くなることが考えられます。モチベーションを損なわないオフィス環境を確保・構築することを考えれば、そのコストはより高まるでしょう。
オフィスへの出社回帰後、ハイブリッドワークの生産性を高める方法
最後に、オフィスへの出社回帰を一部実施しつつ、リモートワークも維持する「ハイブリッドワーク」スタイルについて、つまずきがちなポイントを解消し生産性を高める方法を紹介します。
ルールを作り、運用しながら改善
ハイブリッドワークを導入する際には、運用ルールをしっかり明確化しておきましょう。勤怠ルールや出社ルール、評価ルールなど従業員が疑問に思うことは、誰もが参照できる形で明記しておきます。
ただし、ルールは一度作って終わりではありません。作ったルールに不満が高まることもあるため、常に社員の声を拾いながら定期的にルールを改善していきましょう。
▼関連記事
風通しの良い職場をつくり、快適さと生産性を高めるポイント
出社の目的を明確化し、それに合わせてオフィスを設計
ハイブリッドワークを導入する場合は、なぜ物理的なオフィスへの出社が必要なのかを全社で共有しましょう。
リモートワークでも業務をまわすことに不便しない人は、わざわざ通勤する労力をかけてまでオフィスへ出社したいとは思わないでしょう。出社する意味があることを伝えることで、不満を感じることなく出社してもらえるはずです。
また、出社する目的を達成するための取り組みも必要です。たとえば「出社してコミュニケーションを活発に行ってほしい」と言っておきながら、会社にコミュニケーションするためのスペースがなければ意味がありません。目的に沿ったスペースや制度の整備も進めていきましょう。
▼関連記事
住友ファーマがDXを大切にする理由 ovice導入でシナジーを促進するフロンティア事業推進室
コクヨ代表と考える、これからのハイブリッドワークを支えるワークプレイスのあり方
またそもそもコミュニケーションをあまり必要に感じていない人もいるかもしれませんので、どこから目線を合わせる必要があるのかにも注意を払うといいでしょう。
▼参考
テプコシステムズでのバーチャルオフィス全社導入。“新しい働き方”にoviceが役立つ理由(ovice活用事例)
ハイブリッドワークに適したツールを導入
出社組とリモートワーク組のコミュニケーションをスムーズにするには、バーチャルオフィスも役に立ちます。自宅にいても出社しているのと同じようにコミュニケーションできるため、マネジメントの課題も解決できます。
▼関連記事
Slack、Zoom、ovice…コミュニケーションツール、どう使い分ける? 3つの事例を紹介
みんなが集まるバーチャル空間を提供するバーチャルオフィスツール「ovice(オヴィス)」では、ハイブリッドワークでオフィスに出社するメンバーの位置をバーチャル空間に表示する「位置表示」機能や、オフィスの様子を配信できる「窓」など、様々な機能を開発、実装しています。物理的なオフィスに出社してもリモートワークでも、メンバー同士がコミュニケーションしやすく、シナジーの発揮も期待できます。
▼関連記事
バーチャルオフィスoviceの“窓”を使って感じた予想外の効果
オフィスへの出社回帰を実施するならば、出社の意義を明確に
オフィスへの出社回帰を実施する企業は「出社する意味とは」「オフィスの意義とは」という問いにきちんと向き合わなければなりません。この点を曖昧にしたままオフィスへの出社回帰を号令したのでは、従業員には、納得感が持てないまま意にそわないルールができた、と感じられてしまうかもしれません。
結果として、従業員に不満を溜めさせてしまう、モチベーションを下げてしまうなどということが考えられますし、最悪の場合は人材流出を招いてしまいます。
反対に、オフィスの役割を明確にし出社の意義を定義できれば、柔軟な働き方とアウトプットの両立が期待できます。職場環境と勤務ルールの整備は、市場競争力の強化にもつながる重要な起点だとも言えるでしょう。
出社することのゴールは、メンバー同士のシナジーを発揮することにあるはずです。それは単にコロナ禍以前の働い方に戻すことだけでは実現しません。「新しい働き方への進化」という考えを基盤に、これまでの常識や思い込みを捨て去り、改めて「なぜ出社するのか」を言語化することから始めてみてはいかがでしょうか。
_画像01.jpg)